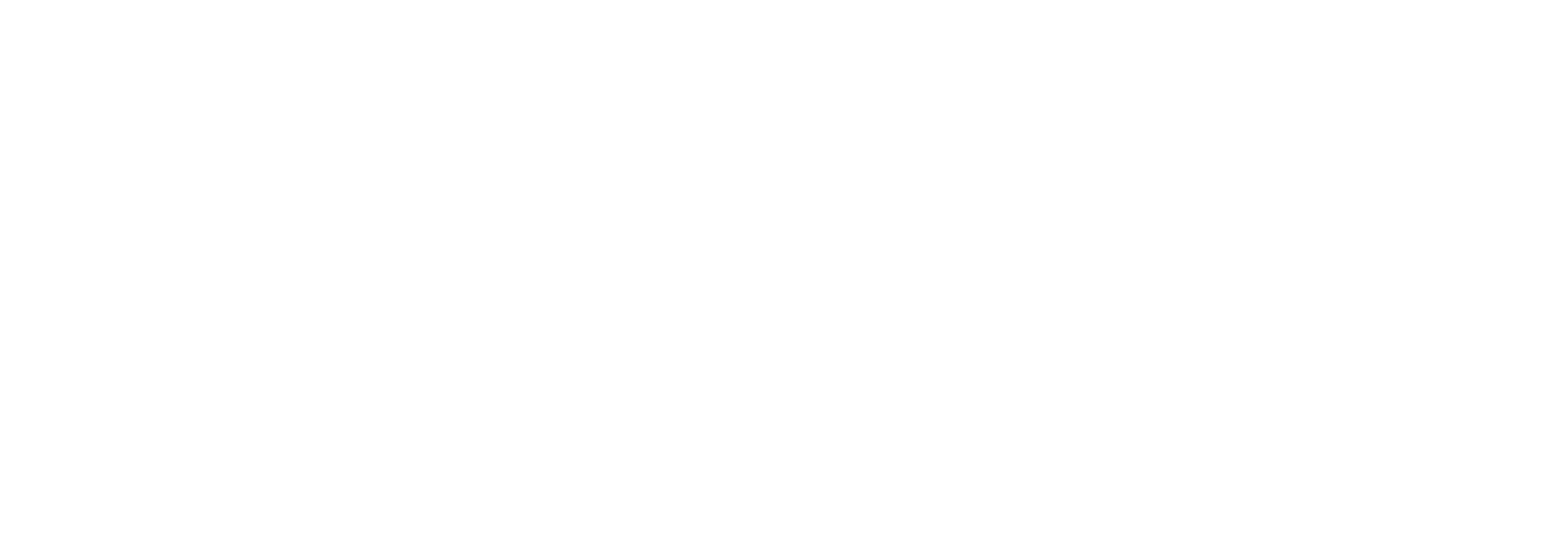
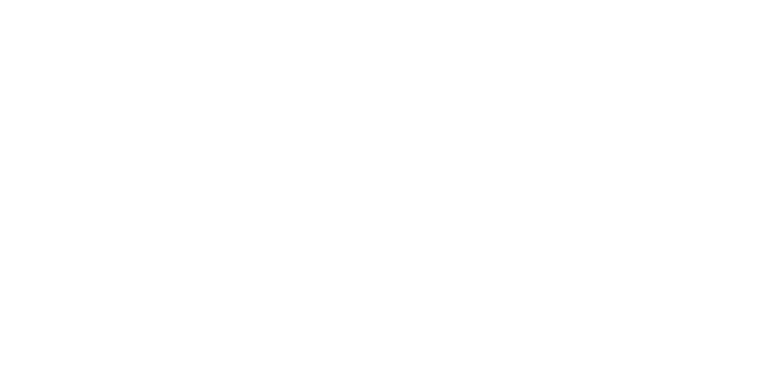
障がい者法定雇用率とは、一定規模以上の事業主に対し一定割合以上の障がい者を雇用するよう義務付ける制度です。これは、障害者雇用促進法に基づき、国・地方公共団体・民間事業者の責務として規定されています。
民間企業の法定雇用率は2024年(令和6年)より2.5%と引き上げられましたが、2026年(令和8年)にはさらに2.7%へと段階的に引き上げられることが決定しており、企業には対応が求められています。
特に中小企業においては「自社だけでの障がい者雇用への対応は難しい」といった声も多く、障がい者雇用対応に向けた「外部支援の活用」も選択肢のひとつとして注目されています。
今回は、障がい者法定雇用率の引き上げに伴う事業者への影響と、企業が取り組むべき対応策について解説します。
障害者雇用促進法は、障がい者の雇用の促進と職業の安定を目的とする法律です。この法律に基づき、常用雇用労働者数が一定以上の企業に対しては、法定雇用率を下回らないよう、身体・知的・精神障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率は、5年に1度、労働市場の動向や経済環境の変化に応じて見直しが行われることとされています。
また、障がい者の雇用義務が生じた企業に対しては、毎年6月1日時点の障がい者雇用状況の報告が義務づけられる他、努力義務として障がい者雇用の促進および定着支援のための「障害者雇用推進者」の選任に対応する必要があります。
企業に求められる障がい者の雇用数は、常用雇用労働者(1年を超えて雇用されている、もしくは雇用される見込みがある労働者)のうち、週の所定労働時間が30時間以上の労働者を1名、20時間以上30時間未満の労働者を0.5名とカウントし、合計に障がい者法定雇用率をかけて算出します。
つまり、2025年時点における民間企業の法定雇用率は2.5%であるため、常用雇用労働者を40名以上雇用している事業主に対して、障がい者を1名以上雇用する義務が発生します。今後2026年7月に雇用率が2.7%に引き上げられた場合、雇用義務の発生ラインは常用雇用労働者数37.5名以上の事業者まで拡大します。
なお、障がい者の区分(手帳の種別)や労働時間に応じて計上方法が異なります。詳細は以下の通りです。

※令和5年4月以降の措置として、精神障がい者かつ短時間労働者については、当面の間1名としてカウント
厚生労働省が発表する「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障がい者の雇用者数は67万7,461.5人、実雇用率は2.41%と、いずれも過去最高を更新しました。
一方で、雇用率の法定基準を達成した企業の割合は46.0%にとどまり、前年から4.1ポイント減少しています。この背景には、令和6(2024)年度より法定雇用率が2.5%へ引き上げられたこと、それに伴い常用労働者数40〜43.5人未満規模の企業が報告対象となったことも挙げられます。
厚生労働省は、令和9(2027)年度に雇用率達成企業の割合を56.0%に引き上げることを目標に掲げていますが、2026年(令和8年)に障がい者法定雇用率2.7%への引き上げが控える中、対象となる事業者の障がい者雇用体制の構築が急務となっています。

障がい者法定雇用率の引き上げは、企業にとって雇用体制の見直しや対応強化を迫る重要な課題となっています。続いては、法定雇用率未達成時のリスクなど、企業に及ぼす具体的な影響について解説します。
企業が障がい者法定雇用率を達成できていない場合、事業主は一定のペナルティを受ける可能性があります。
まず、常用雇用労働者数が100名を超える企業において、雇用率が未達成である場合には、不足する人数に応じて「障害者雇用納付金」(1人あたり月額5万円)を納付する義務が生じます。ただし、徴収された納付金は、障がい者を多く雇用する事業主に対し、調整金や報奨金、助成金として支給されます。
また、雇用率未達成の企業に対しては、ハローワークから「障がい者雇入れ計画」の作成命令が出される可能性があります。さらに計画を実施しない企業に対しては企業名公表の対象となることもあります。これらの対応は企業の社会的信用や採用活動にも影響を与えることから、早期の障がい者雇用体制の整備が求められます。
障がい者法定雇用率の引き上げにより、企業は新たに一定数の障がい者を雇用する義務を負うこととなります。これに伴い、採用活動の強化が不可欠となりますが、近年の構造的な労働力不足の状況では、既に「採用活動そのものが困難である」との声も多く、障がい者人材の確保に一層の難しさが加わっています。
また、障がい者の雇用人数の増加に伴い、他の従業員の負荷増や業務への影響も無視できません。厚生労働省の調査によれば、障がい者の雇用に関する課題について「ある」と回答した事業者は63.0%にのぼりました。内訳としては、77.2%が「会社内に適当な仕事があるか」、47.4%が「職場の安全面の配慮が適切にできるか」、そして41.7%が「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」としています。この結果は、当事者に適した業務の切り出しや社内体制の整備、そして社内の意識向上といった、多層的な対応の必要性を示しています。
さらに、障がい者雇用の推進は、企業全体の経営戦略に直結する課題ともいえます。具体的には、人的リソースの再配分や育成計画の見直し、業務プロセスの再検討といった取り組みが求められ、これらにかかる人的コストの負担増は、特に中小企業においては大きな課題と言えます。
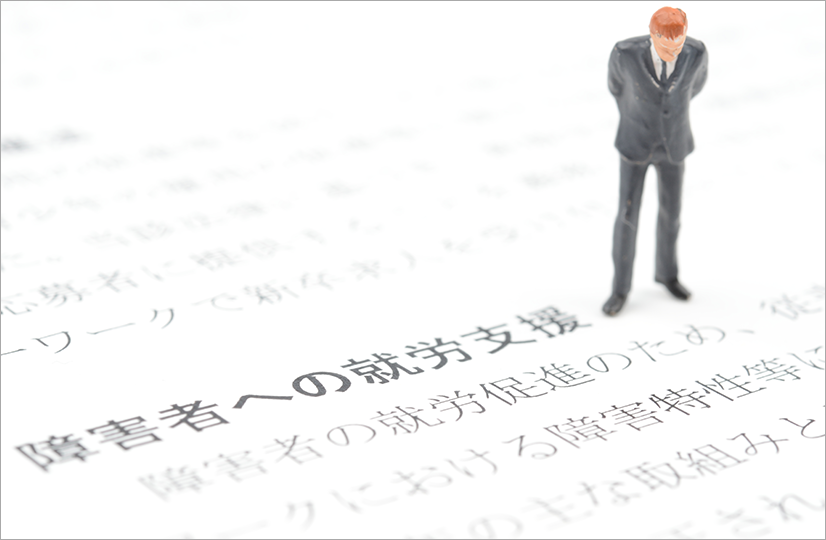
法定雇用率の引き上げや社会的要請の高まりを受けて、企業は障がい者雇用の強化を求められています。しかし、雇用の推進を自社単独で行うには、採用・定着の両面で多くの課題が伴います。
障がい者雇用では、企業が求める人材と応募者の特性とのミスマッチがしばしば課題となります。とりわけ、雇用においては障がいの区分として身体障がいに偏る傾向が依然として強く、知的障がい者や精神・発達障がい者の雇用が進みにくい状況にあります。
実際に、厚生労働省の令和5年のデータによると、雇用されている障がい者の内訳は、身体障がい者が52.6万人に対し、知的障がい者は約27.5万人、精神障がい者は約21.5万人、発達障がい者は約9.1万人と、身体障がい者に大きく偏っています。さらに、事業主の7割以上が「会社内に適当な仕事があるか」つまり、障がい者の特性に合わせた業務を用意できるかを課題として挙げているように、多様な障がい特性を理解したうえで、適切な職域を設計することが不可欠です。
採用後の受け入れ体制が整っていないことも、大きな障壁となります。合理的配慮を行うための設備や支援体制が不十分であったり、社内の理解が不足していたりする場合、障がい者が職場で孤立しやすくなり、早期離職につながるケースも少なくありません。
配属先の教育やフォロー体制が整備されていないと、適応が困難になり、結果として採用コストの負担が増すことにもなります。障がい者雇用を形式的に進めてしまうことで、むしろ企業にとっての負担が大きくなるリスクがあるのです。

障がい者雇用を円滑に進めるためには、採用活動だけでなく、採用後の受け入れ体制の構築、適切な職域設計、さらには社内全体の意識改革までを含めた、計画的かつ持続的な取り組みが欠かせません。
特に、知的障がいや精神・発達障がいなど、多様な特性を持つ人材が安定して働ける環境を整えるには、企業単独で対応するには限界があるのが実情です。そのため、専門的知識と実績を持つ外部機関による支援が、ますます重要視されています。
実際の現場では、以下のような外部支援を受けることで、障がい者雇用の定着率を高め、職場全体の受け入れ態勢を整えることが可能になります。
●障がい特性に応じたマッチング支援
●業務の切り出しや、職場環境整備に関するコンサルティング
●採用後の定期的な面談やフォローアップ体制の構築
●受け入れ部署への具体的な対応アドバイス
●社内研修や啓発活動による従業員の理解促進
企業と障がい者の間に立ち、双方の橋渡しを行うことで、障がいを持つ人材が長期的に活躍できる職場環境の実現が可能となります。

障がい者雇用に向けた体制を、企業単独で整えることは容易ではありません。そこで注目されているのが、特例子会社など外部機関による支援サービスの活用です。ここでは、企業の障がい者雇用支援を実現する、株式会社平山LACC(ラック)の障がい者雇用サポート事業についてご紹介します。
株式会社平山LACCは、企業の社会的責任(CSR)を踏まえ、障がいのある方々に対して安心して働ける職場環境と、能力を最大限に発揮できる機会を提供する特例子会社として、2017年6月に設立・認定を受けました。以来、障がい者の自立と社会参加の促進を使命に、就労支援と雇用機会の創出に取り組んでいます。
昨今、障がい者法定雇用率の引き上げや、インクルーシブな社会実現への意識の高まりにより、多くの企業が障がい者雇用に取り組んでいます。しかし現実には、身体障がい者に雇用が偏る傾向があり、知的障がいや精神障がいのある方々の採用・雇用は、依然として進みにくい状況があります。
こうした課題に対応するため、平山LACCでは多様な障がい特性に配慮した職場環境を整備。誰もが安心して働ける体制を構築し、企業と障がい者の双方にとって持続可能な雇用の実現を支援しています。
平山LACCは、障がい者雇用に課題を抱える企業に対し、オフィス環境の提供から人材支援、職域開発、採用支援、行政・地域機関との連携まで、包括的かつ一貫した支援をワンストップで行っています。
共同作業スペースの提供
障がい特性に配慮したオフィス環境を整え、障がい者が安心して働ける共同作業スペースを用意しています。現場には各障がいの特性を理解した経験豊富な支援スタッフが常駐し、業務のフォローを行います。
採用支援
地域のハローワークや職業訓練機関などと連携し、企業の採用活動を多方面からサポートします。各企業に適した人材の紹介や、採用プロセスに関する助言など、実務に即した支援を展開しています。
職域開発コンサルティング
企業ごとの業務内容や職場環境に合わせて、障がい者が取り組みやすい業務を設計・提案。職務の切り出しや業務設計、環境整備などを含む職域開発のコンサルティングを通じて、安定した就労の実現を支援します。
法定雇用率の達成に向けて障がい者雇用を進めるうえで、多くの企業が直面しているのは「どのように受け入れ、どのように活用すべきか」といった具体的な実務の課題です。しかし、職場環境の整備や職域の設計、さらには日常的なサポート体制の構築まで、企業が単独で対応するには限界があります。
そこで求められるのが、専門的な知見と現場に即した実践的な支援です。平山LACCでは、採用時のご相談から、業務の切り出しや環境整備、そして配属後の継続的なフォローアップまで、企業と障がいのある方の双方に寄り添った総合的なサポートを提供しています。障がい者雇用に関するご不安や課題は、お気軽に平山LACCまでご相談ください。
障がい者雇用促進定着支援コンサルティング| 株式会社平山LACC
「現場改善コンサルティング」「製造請負」「製造派遣・人材紹介」という事業の中で培った社員教育ノウハウを活かし、出張セミナーや研修運営等さまざまな人材教育事業を提供しております。
研修・セミナーの内容もご要望に応じてカスタマイズすることもできます。人材の育成・教育にお悩みでしたら御気軽にお問い合わせください。
・安全衛生 / 「安全配慮義務セミナー」 「職長教育」 「安全管理者専任研修」 等
・改善 / 「トヨタ実践道場」 「IEの基礎」 「職場改善の進め方」 等
・コスト / 「コストダウン手法」 「実践・原価管理」 「企業会計財務諸表の見方」 等
・新卒関連 / 「社会人としての心得とマナー」 「生産活動と5Sの基本] 等
・生産 / 「生産管理の基礎」 「5S」 「TPMと設備保全」 等
・品質 / 「現場で役立つ品質管理」 「現場力を高めるISO9001」 等
・マネジメント / 「仕事のムダの改善と問題解決」 「管理者の役割と責任」 「労務管理とメンタルヘルス」 等
・労務 / 「法務研修」 「適正請負セミナー」 「派遣法セミナー」等
短期的な人員の補充には「派遣」、正社員雇用が必要な場合は「紹介」という形で、お客様のご要望にマッチした、即戦力となる人材をお届けいたします。
製造業における技術はもちろん、「充実した教育体制(ソロフライトプラン)」と「カウンセリングシステム(ココロケアサポート)」を取り入れ、ヒューマンスキルも備えた優秀な人材を育成しております。
「機械設計」「電気電子設計」「ソフトウエア開発」「プラント設計」など、高度な技術力を要求されるこれらの分野でも高い評価をいただいています。
トップレベルのスキルを持つエンジニアから、サポートを行うスタッフまで、幅広い技術者を取りそろえて、お客様の開発環境の最適化を支援しています。開発&設計技術者派遣事業については、平山グループ内の(株)トップエンジニアリングが担当いたします。

御依頼や御相談がある方は、以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。翌営業日までにeメールまたはお電話にてお答えさせていただきます。
※土・日曜日、祝祭日、当社の年末年始休暇期間中のお問い合わせは、翌営業日以降のお返事とさせていただきます。また、お問い合わせの内容や件数等により、お返事が遅れる場合がありますこと、ご了承ください。